防災と男女共同参画
平成28年4月に発生した熊本地震は、幸いにも荒尾市には大きな被害をもたらしませんでしたが、みなさんの地震に対する考え方、心構えなどには、少なからずとも影響を与えたのではないでしょうか。
いざ災害が起きたときに、自分の身を守るため、大切な人を守るために、普段からできることを、男女共同参画の視点で紹介します。
男女共同参画って???
人と人とがお互いに対等なパートナーとして認め合い、支え合いながら、だれもが自分らしさや自分の能力を十分に活かした生き方ができるよう、みんなが責任をもって協力し合うことです。
災害発生!その時あなたは?
- 家族の安否確認の方法(連絡方法、集合場所など)を決めている
- 学校や保育園、幼稚園へ誰が子どもを迎えに行くかを決めている
- 自分が住む地域の避難場所を知っている
- 水や食べ物などを普段から備蓄している
- 災害時に持ち出すものを準備している
- 公衆電話がある場所を知っている
- 近所に協力し合える人がいる
災害へのモノの備えはもちろんのこと、日頃から、家族で、地域で、みんながともに声をかけ合い、協力し合えるつながりを作っておくことが、災害時の防災力アップにつながります。
避難所と男女共同参画(避難所ではこのような課題が起こりやすいと言われています)
- 世帯状況や個人の抱える事情に関わらず、男性は力仕事、女性は炊き出しに負担が集中する
- 子どもが騒ぐ、夜泣きすることによるストレス(子どもの親、避難者双方)
- 避難所運営リーダーはほとんどが男性で、女性の声が届かない
- 女性用の更衣室や洗濯物干場、授乳室がない
- 生理用品、粉ミルク、オムツがない
- 普段から地域との交流がない避難者の孤立
「防災=男性が担うもの」という思い込みをなくし、老若男女すべての人が避難所運営に主体的に関わり、いろいろな立場の人がお互いに気持ちよく過ごすことができる、居心地のいい避難所づくりをみんなで考えることが必要です。地域で行われる防災訓練などに積極的に参加しましょう。
普段の暮らしの中に男女共同参画の視点を!
災害時は、普段の生活の中で抱えている問題がさらに浮き彫りとなってあらわれます。
だからこそ、普段の暮らしの中に男女共同参画の視点を取り入れることがとても重要になってきます。普段できていないことは非常時にはもっとできません。
いざ災害が起きたとき、自分自身を、そして大切な人を守れる自分でいるために、まずは普段の生活の中か「男だから」「女だから」と性別で役割を決め付ける考え方をなくし、人とのつながり、地域とのつながりを大切にしながら、お互いに思い合い支え合える関係づくりをはじめましょう。

 こども・子育て
こども・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者 休日当番医
休日当番医 ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクル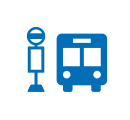 公共交通
公共交通 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引っ越し
住まい・引っ越し 就職・退職
就職・退職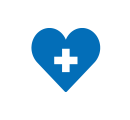 病気・けが
病気・けが おくやみ
おくやみ 施設案内・予約
施設案内・予約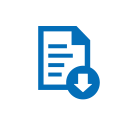 電子申請・申請書様式
電子申請・申請書様式 相談窓口
相談窓口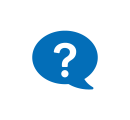 よくある質問
よくある質問 市長室へようこそ
市長室へようこそ 荒尾市議会
荒尾市議会 市政に参加する
市政に参加する 入札・契約
入札・契約





