男性にとっての男女共同参画について~男性がいきいきと活躍できる社会を目指して~
男女共同参画社会とは、いろいろな生き方を尊重し、すべての人があらゆる場面で活躍できる社会のことです。
つまり、女性にとってだけでなく、男性にとっても暮らしやすい社会のことなのです。
男女共同参画社会の実現に向けた大きな障がいの一つとなっていることに「固定的性別役割分担意識」があります。これは、わたしたちの意識の中に長い時間をかけて形づくられてきたもので、時代とともに変わりつつあるものの、今も依然として根強く残っています。この、固定的性別役割分担意識は、女性自身のみならず、男性自身にとっても重荷になっている、とも言われています。
子育ての現場で
子育てを楽しんだり、料理を趣味にする男性や、家事を積極的に行う男性が増えています。しかしながら、日本の男性が家事や育児に費やす時間は世界的にみると最低の水準となっています。これは、女性に比べて男性の長時間労働が多く、家庭で過ごす時間が少ないことがひとつの要因であると考えられています。
また、育児休業を取得したいと思いながらも、周りの理解が得られず、また、自身の金銭面・仕事面での不安から、取得できずにいる男性がたくさんいます。
介護の現場で
家族形態の変化や高齢世帯の増加、共働き世帯の増加等のため、男性の介護者が増えています。しかし、男性が介護者となることについては、さまざまな問題が生じることがあるようです。
男性は家事に不慣れな方が多いことから、女性の介護者に比べて苦労が多かったり、さらにその苦労や悩みを誰にも相談できず、ストレスをため込んでしまう傾向があるようです。
このような状況の背景には、男性自身の意識の中に、「一家を経済的に支えるのは男性の役割である」、「男は弱音をはくべきではない」等の「固定的性別役割分担意識」がみられる場合があります。
「男はこうあるべき!」といった考え方が、家庭や職場、地域など様々な分野へ男性が進出していくうえでの障がいとなっていることがあるのです。
男性にとって、男女共同参画社会実現のメリットは、「自分自身への重すぎるプレッシャーを減らせること」ではないでしょうか。まずは、男性自身の「男性に対する固定的性別役割分担意識」を解消することで、男性がより暮らしやすくなる社会への第一歩を踏み出してみませんか?

 こども・子育て
こども・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者 休日当番医
休日当番医 ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクル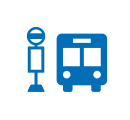 公共交通
公共交通 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引っ越し
住まい・引っ越し 就職・退職
就職・退職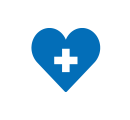 病気・けが
病気・けが おくやみ
おくやみ 施設案内・予約
施設案内・予約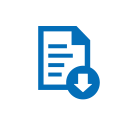 電子申請・申請書様式
電子申請・申請書様式 相談窓口
相談窓口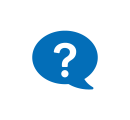 よくある質問
よくある質問 市長室へようこそ
市長室へようこそ 荒尾市議会
荒尾市議会 市政に参加する
市政に参加する 入札・契約
入札・契約






