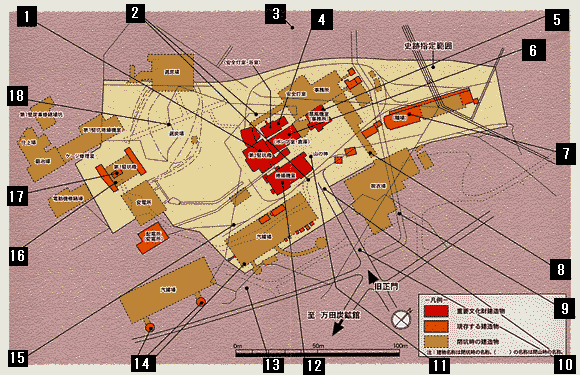万田坑構内 見所マップ
1
第二竪坑櫓
 やはり、万田坑のシンボル。保存修理により操業当時のように綺麗になりました。
やはり、万田坑のシンボル。保存修理により操業当時のように綺麗になりました。
明治41年完成。隣接する巻揚機によりワイヤーが巻かれ、吊るされたケージ(昇降用エレベータ)が上下していました。ケージは2つ吊り下げられ、一方が上がると他方が下がるつるべ式となっていました。上部の滑車(矢弦)が人員昇降用で、下部の滑車は資材搬入用でした。
第二竪坑坑口
 ここから坑内に降ります。誰もがたたずみ、見入ってしまいます。
ここから坑内に降ります。誰もがたたずみ、見入ってしまいます。
明治41年完成。人員昇降および排水、排気の用途として利用され、石炭は揚げていません。昭和26年閉坑以降は、三池炭鉱坑内の維持管理用として平成9年閉山時まで使用されていました。竪坑深さは約274mありましたが、閉山時に選炭場の土砂により埋め立てられました。
2
屋外に保管されているケージ
草むらの中にシートをかけられ保管されています。また、巻揚機室南にも1つ保管されています。保管の状態に不安もありますが、これらが櫓に取り付けられれば・・・・・。
3
三池炭鉱専用鉄道敷跡
三池炭鉱の変遷を読み解く貴重な歴史資源。高取山、万田山、四山といった主要な丘陵地の山裾を順次炭鉱開発していた痕跡が、炭鉱専用鉄道敷跡には示されています。地域の地形構造に沿った開発で、大牟田、荒尾両市の都市の成り立ちをたどることができる路線です。
4
閉山時の安全燈室
この建物は、明治期は隣接する扇風機室に関連する機械室であったようで壁面に多くの痕跡が残っています。万田坑の建物の中でも最も古いものの一つで、用途の変更が頻繁に行われています。
昭和26年の閉坑後、三池炭鉱の坑内管理のため安全燈室として使用されました。安全燈(ヘルメットライト)の充電器が現存しています。
閉山時の浴室
閉坑後、浴室として使われていました。全盛期の大規模な浴室と比べるとかなり小さいが、当時の様子は想像できます。
5
閉山時の事務所内部
昭和26年の閉坑後、扇風機室から事務所として用途が変わり使用されていました。湯呑みやロッカー、カレンダーなどそのままの状態で残っています。
 大正3年頃の建物で、当初は巨大な扇風機が置かれた扇風機室でした。そのころは、この建物の北側に安全燈室、事務所が隣接しており、その痕跡が西側壁面に残っています。また、南側壁面には向かいのポンプ室および倉庫に繋がった痕跡が見て取れます。
大正3年頃の建物で、当初は巨大な扇風機が置かれた扇風機室でした。そのころは、この建物の北側に安全燈室、事務所が隣接しており、その痕跡が西側壁面に残っています。また、南側壁面には向かいのポンプ室および倉庫に繋がった痕跡が見て取れます。
※事務所内には入れません。
6
閉山時のポンプ室、倉庫
 坑内排水用のポンプが置かれていました。現在も地下に灌漑用水槽があります。
坑内排水用のポンプが置かれていました。現在も地下に灌漑用水槽があります。
全盛期(明治38年~大正3年頃)、ここは坑内の換気を行う巨大な扇風機が置かれていました。現在も扇風機の痕跡やレンガ造りの排気用煙突が残っています。現在38年完成の建物で最も古い建物の1つです。
※ポンプ室内には入れません。
7
工作機械が満載の職場
 北の外れにあり、ちょっと見落としがち。かつて職場と呼ばれ、万田坑のメンテナンスを行っていました。
北の外れにあり、ちょっと見落としがち。かつて職場と呼ばれ、万田坑のメンテナンスを行っていました。
昭和初期の建物。現在、屋根の一部が落ちてしまっていますが、内部には万田坑内の機械や設備を修理する工作機械が、数多く残っています。
8
かつての脱衣所と事務所を結ぶ通路の痕跡
 かつて、このあたりには、桜並木がありました。
かつて、このあたりには、桜並木がありました。
構内側からの写真。
脱衣場を通り、ここから事務室や繰り込み場、安全燈室を経て坑内作業へ向かっていたようです。このような構内の様子を探る貴重な手掛かりです。
9
大牟田とつながる当時の生活通路(地下通路)
昭和8年頃設置されました。荒尾市側から万田駅を利用でき、大牟田市側から万田坑、倉掛商店街等の施設を利用できるように設けられたといわれています。数年前まで使われていましたが、現在は安全性確保のため、閉鎖されています。
10
正門
全盛期の正門は手前の門柱位置。この正門を通り右側にあった脱衣場と呼ばれていた大きな建物を通り構内へ入っていきました。
旧正門手前、右側のバリケードは桜町トンネルの入口。
奥に見えるのが現在の正門です。
11
山ノ神
坑内へ降りる作業員は、必ず入坑前に安全を祈願していました。
石祠(せきし)が大正5年、灯ろうが大正6・7年、花立てが大正15年、狛犬、賽銭箱が昭和5年のものです。
12
炭鉱マンの命を支えた巻揚機とワイヤー
中2階にある機械は、資材巻き上げ用のウインチ。2階にある機械が人員を昇降させるケージを巻き上げるものです。内部の壁面には、機械の仕様、信号(合図)、操作上の注意事項等が貼ってあり、当時の雰囲気が伝わってきます。
13
第二竪坑
 赤煉瓦が印象的です。このあたりが、第二竪坑櫓と巻揚機室が美しく見えるベストポイント。
赤煉瓦が印象的です。このあたりが、第二竪坑櫓と巻揚機室が美しく見えるベストポイント。
櫓は明治41年完成、高さは18.8m。巻揚機室は明治42年完成、煉瓦造2階建てとなっています。
14
大活躍したシンボル。煙突と汽罐場跡
汽罐場は石炭を燃やして蒸気を発生させ、万田坑の各施設へ供給していました。現存する壁は、明治期のもの。建物と並行して2本の煉瓦造の煙突がそびえていました。全盛期(昭和初期まで)は、汽罐場が3棟あり、煙突も5本ありました。
15
レールの上にポツンと残る炭がん
 なぜかこの風景に魅せられてしまいます。「今昔・・・・・」
なぜかこの風景に魅せられてしまいます。「今昔・・・・・」
炭がんは石炭を運搬する炭車のことです。(写真は坑外にある台車)
16
第一竪坑櫓の巨大なコンクリート基礎
このコンクリート基礎の上に高さ30.7mの櫓が建っていました。当時東洋一の高さと呼ばれていました。昭和29年に北海道芦別炭鉱第一竪坑に移築され、再利用されましたが、現存していません。
17
今も開口する第一竪坑口
 竪坑深さ273mは、横浜ランドマークタワーとほぼ同じ高さ。そばに立つと足がすくみます。
竪坑深さ273mは、横浜ランドマークタワーとほぼ同じ高さ。そばに立つと足がすくみます。
第一竪坑は、直接石炭を採掘していた施設で、昭和26年の閉坑以前の中心施設です。第一竪坑周辺の施設は、閉坑後ほとんど取り壊されていますが、坑口は坑内吸気道確保のため、現在も開口しています。寒い日は、地熱の関係で蒸気が上がっているのが見えます。
18
ちょっと高台の選炭場跡
第一竪坑から採炭された石炭を選炭、運搬する施設がありました。選別された石炭は、炭鉱鉄道で三池港に直接運ばれました。閉山時に第二竪坑内を埋めるため、選炭場を削ったので現在の高さになりました。地下には第一、第二坑を結ぶトンネルがあります。

 こども・子育て
こども・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者 休日当番医
休日当番医 ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクル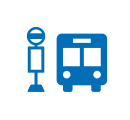 公共交通
公共交通 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引っ越し
住まい・引っ越し 就職・退職
就職・退職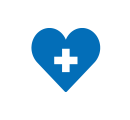 病気・けが
病気・けが おくやみ
おくやみ 施設案内・予約
施設案内・予約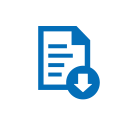 電子申請・申請書様式
電子申請・申請書様式 相談窓口
相談窓口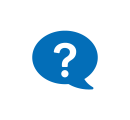 よくある質問
よくある質問 市長室へようこそ
市長室へようこそ 荒尾市議会
荒尾市議会 市政に参加する
市政に参加する 入札・契約
入札・契約