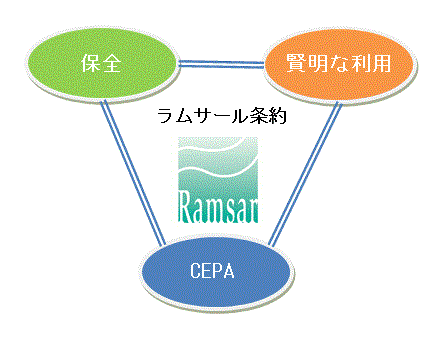ラムサール条約湿地 荒尾干潟
荒尾干潟は平成24年7月3日付けで、ラムサール条約湿地に世界で2,054番目に登録されました。
日本国内の干潟の約40%が現存する有明海で初めての登録となり、また日本国内で最も干潟を保有している熊本県内でも初めての登録となります。
登録面積
754ヘクタール
保護の形態
国指定鳥獣保護区特別保護地区[下図の赤枠(荒尾干潟)の範囲]
(写真:西村誠)
ラムサール条約とは
正式名称
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」
1971年に「湿地および水鳥の保全のための国際会議」が開催されたイランのラムサールで条約が採択されたため、「ラムサール条約」と呼ばれています。
目的
特に水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地およびそこに生息する動物や、生育する植物の保全の促進
締約国が採るべき措置
- 各湿地の管理計画の作成、実施(保全と賢明な利用の推進)
- 各条約湿地のモニタリング、定期的な報告
- 湿地の保全に関する自然保護区の設定
- 湿地の保全管理に関する普及啓発、調査の実施
ラムサール条約の柱
- 保全・再生
水鳥だけでなく私たち人間にとっても重要である湿地を保全・再生する - 賢明な利用
湿地の体系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に活用する(ワイズユース) - 交流・学習(CEPA)
湿地の保全や賢明な利用のために人々の交流や情報交換、教育などを進める
備考 CEPA:Communication, Capacity building, Education, Participation and Awareness
ラムサール条約湿地とは
条約に基づく「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録された湿地のことです。
ラムサール条約の締約国は、自国の湿地を条約で定められた以下の国際的な基準(9つの基準)に沿って、条約事務局が管理する「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載します。これが「ラムサール登録湿地(Ramsar site)」です。
国際的な基準
基準1
特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、または希少なタイプの湿地
基準2
絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地
基準3
生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地
基準4
動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地
基準5
定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地
基準6
水鳥の1種または1亜種の個体群で、個体数の1%以上を定期的に支えている湿地
基準7
固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支えている湿地。また湿地というものの価値を代表するような、魚類の生活史の諸段階や、種間相互作用、個体群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献するような湿地
基準8
魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な湿地。あるいは湿地内外における漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地
基準9
湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種および亜種の個体群で、その個体群の1%を定期的に支えている湿地 (※魚類:魚・エビ・カニ・貝類)
- 基準1:湿地に関する基準
- 基準2、3、4:種および生態学に関する基準
- 基準5、6:水鳥に関する基準
- 基準7、8:魚類に関する基準
- 基準9:動植物に関する基準
日本での登録条件
- 国際的に重要な湿地であること(国際的な基準のうちいずれかに該当すること)
- 国の法律(自然公園法、鳥獣保護法など)により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること
- 地元住民などから登録への賛意が得られること

 こども・子育て
こども・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者 休日当番医
休日当番医 ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクル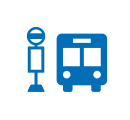 公共交通
公共交通 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引っ越し
住まい・引っ越し 就職・退職
就職・退職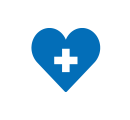 病気・けが
病気・けが おくやみ
おくやみ 施設案内・予約
施設案内・予約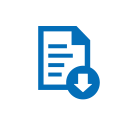 電子申請・申請書様式
電子申請・申請書様式 相談窓口
相談窓口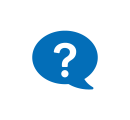 よくある質問
よくある質問 市長室へようこそ
市長室へようこそ 荒尾市議会
荒尾市議会 市政に参加する
市政に参加する 入札・契約
入札・契約