1 荒尾市内小中学校の教員の勤務時間の実態
| 荒尾市教職員 | 国の基準360時間との差 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 小学校 | 404‘54 | 378‘17 | 44‘54 | 18‘17 |
| 中学校 | 516‘31 | 479‘15 | 156‘31 | 119‘15 |
| 市全体 | 444‘08 | 410‘15 | 84‘08 | 50‘15 |
| 月45時間以上 | 月80時間以上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 小学校 | 28.1% | 27.1% | 1.7% | 1.3% |
| 中学校 | 44.0% | 39.1% | 8.8% | 4.7% |
| 市全体 | 33.3% | 31.0% | 4.0% | 2.4% |
- 年間の一人あたりの時間外勤務の状況は、国の基準を超えており、特に中学校は大きく超えている。
- 全体の約3割の職員が月45時間を超え、月80時間を超える職員は、小学校においては微減し、中学校においては若干減少している。
- 月ごとの勤務時間を比べると、4月から6月と9月から11月に超過の傾向が見られる。
- 教頭や一部の教諭等に超過勤務の固定化の傾向が見られる。
- 時間外勤務の主な理由は、小中学校ともに教材研究及び諸調査等の事務処理が挙げられる。また、中学校では部活動及び校務分掌も主な理由となっている。
以上の実態を踏まえ、本市教員の健康の保持と教育の質の維持・向上を図るためには、学校の働き方改革が引き続き喫緊の課題であると捉える。
そこで、荒尾市教育委員会は「荒尾市立小中学校の教員の勤務時間の上限に関する方針」を策定し、実効性のある取組を進めるために、学校現場の声を聞きながら、できるところから確実に実施していく。
2 荒尾市立小中学校の教員の勤務時間の上限に関する方針
1 学校における働き方改革が目指すもの
教員の業務負担の軽減を図り、限られた時間の中で、教員の専門性を生かしつつ、授業改善のための時間や子どもたちに接する時間を十分確保し、教員がこれまでの学校教育の蓄積と向かい合って、自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を持続的に行うことができるようにする。
2 勤務時間の上限に関する指針策定の目的
- 業務の総量を削減し、教員が疲労や心理的負担を過度に蓄積して、心身の健康を損なうことがないようにする。
- 教員が自らの専門性を高め、教育活動を充実させることにより、これまでの教育の質を維持・向上させる。
3 上限の目安時間
- 勤務を要する日の在校時間について、条例等で定められた1日の勤務時間(7時間45分)を超えた時間(以下「超過勤務時間」という。)の1か月の合計が、45時間を超えないようにすること。
- 勤務を要する日の在校時間について、超過勤務時間の1年間の合計が360時間を超えないようにすること。
4 特例的な扱い
- 上記3を原則としつつ、子どもたちに係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合についても、勤務を要する日の在校時間のうち、超過勤務時間の1年間の合計が720時間を超えないようにすること。この場合においては、勤務を要する日の在校時間について、超過勤務時間の1か月の合計が45時間を超える月は、1年間に6月までとすること。
- 1か月の超過勤務時間が100時間未満であるとともに、連続する複数月(2か月、3か月、4か月、5か月、6か月)のそれぞれの期間について、各月の超過勤務時間の1か月当たりの平均が80時間を超えないようにすること。
5 実効性の担保のために
- 方針の実効性を担保するために、服務監督権者である教育委員会は以下の取組を進める。
① 教育委員会は学校及び教員と協働して、「教員の長時間勤務縮減に向けた取組」を進めるためにアクションプランを作成し、「学校における働き方改革」を総合的に推進する。
②教育委員会は、勤務時間の上限の目安時間を超えた教員がいる場合には、教員の所属する学校の業務や環境整備等の状況について検証する。
③教育委員会は、市長とこの方針について認識を共有し、市長の求めに応じて必要な報告を行うなど連携して取り組む。 - 教育委員会は、保護者を含めて社会全体が方針等の内容を理解できるよう、教育関係者はもちろん、保護者や地域住民等に対し広く周知を図る。
6 その他の留意事項
- この方針は、上限の目安時間まで教員が在校等したうえで勤務することを推奨するものではない。また、上限の目安時間の遵守のみを求めるものではない。
- 教員は、上限の目安時間の遵守を形式的に行うことを優先し、真に必要な教育活動をおろそかにすることがあってはならない。また、虚偽の時間の記録を残したり、残させたりしてはならない。さらに、目安時間を守るために自宅に持ち帰って業務を行ったりすることは、厳に避ける。
- 在校時間は、ICTの活用により客観的に計測し、校外の時間についても本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測する。
- この方針の実施に当たって、教員の休憩時間や休日の確保等、労働法制を遵守する。
- 教員の健康及び福祉を確保するために、次のことに留意する。
①在校時間が一定時間を超えた教員への、医師による面接指導や健康診断を実施する。
②退勤から出勤までに一定の時間を確保する。
③年次有給休暇等の休日について、まとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進する。
④心身の健康問題についての相談窓口を設置する。
⑤必要に応じて産業医等による助言・指導を受け、また、教員に産業医等による保健指導を受けさせる。 - 教育委員会は、「教員の長時間勤務縮減に向けた取組」の実効性を高めるために、社会の動きや教育現場の声を大切にしながら検討を続けていく。

 こども・子育て
こども・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者 休日当番医
休日当番医 ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクル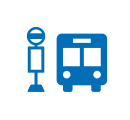 公共交通
公共交通 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引っ越し
住まい・引っ越し 就職・退職
就職・退職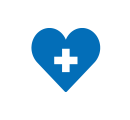 病気・けが
病気・けが おくやみ
おくやみ 施設案内・予約
施設案内・予約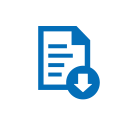 電子申請・申請書様式
電子申請・申請書様式 相談窓口
相談窓口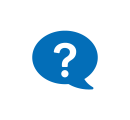 よくある質問
よくある質問 市長室へようこそ
市長室へようこそ 荒尾市議会
荒尾市議会 市政に参加する
市政に参加する 入札・契約
入札・契約





