国民健康保険制度は、病気やケガをした時に、安心して医療が受けられるように加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。
加入者の皆様によって納められた保険税は、国の補助金などと合わせて、皆様の医療費や介護の給付の費用に充てられます。
加入者の皆様にはご負担が生じますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
国民健康保険税は、他の健康保険をやめたときや他の市町村から転入してきたときなど、国保の資格を得たときから課税されます。
資格の届出が遅れると、遡及して保険税を納めていただくことになります。
納税義務者
保険税の納税通知書は世帯主宛に送付されます。世帯主が勤務先の健康保険などに加入していて国保の資格がなくても、世帯の誰かが国保の資格があれば、世帯主が保険税を納める義務があります。(ただし、保険税がかかるのは加入者の分だけです。)
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税(年税額)は下表のように計算します。 (令和7年度以降)
国民健康保険税の試算をする場合は下記をご利用ください。
国民健康保険税の試算ができます
表:国民健康保険税の計算方法
| 区分 |
医療分 (0歳から74歳) |
後期高齢者支援金等分※
(0歳から74歳)
|
介護分(40歳から64歳) |
| 所得割(1) |
(前年の所得-43万)×9.0% |
(前年の所得-43万)×3.3% |
(前年の所得-43万)×2.3% |
| 均等割(2) |
被保険者の人数×26,000円 |
被保険者の人数×7,500円 |
被保険者の人数×8,900円 |
| 世帯割(3) |
一世帯あたり23,200円 |
一世帯あたり7,300円 |
一世帯あたり5,700円 |
| 合計 |
(1)+(2)+(3)
上限66万円
|
(1)+(2)+(3)
上限26万円
|
(1)+(2)+(3)
上限17万円
|
対象者が0歳から74歳の場合、医療分と後期高齢者支援金等分が課税されます。
そのうち、世帯の中に40歳から64歳の対象者がいる場合には、医療分と後期高齢者支援金等分にあわせて、介護分も課税されます。
基礎控除に相当する43万円は合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
後期高齢者支援金とは…
平成20年度より開始された後期高齢者医療制度の財源は、公費5割、被保険者の保険料1割、健康保険組合等(国民健康保険、共済組合等)が約4割負担することになっています。
加入者が後期高齢者医療制度へ移行した際に、国民健康保険税の急激な変動が生じないように軽減措置があります。
1.所得の低い人の国保税の軽減が引き続き受けられます。
例えば、夫婦2人世帯で国保税の所得による軽減を受けていた場合、夫が国保から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯構成および夫婦の収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
2.世帯ごとにご負担いただく国保税の世帯割が半額になります。
例えば、夫婦2人で国保に加入していた世帯について、夫が国保から後期高齢者医療制度に移った結果、国保の加入者が一人となった場合、妻の国保税(医療分・後期高齢者支援金分)の世帯割が、5年間、半額となります。
後期高齢者医療制度へ移行後の5年間の経過措置でしたが、世帯構成が変わっていない世帯については、さらに3年間に限り延長することが決定し、世帯割を4分の1減額することとなりました。
3.被用者保険の被扶養者であったが、新たに国保の被保険者になる場合、国保税の軽減が受けられます。(申請が必要です)
例えば、夫婦2人の世帯で、夫(75歳以上)が会社の健康保険に加入していた場合に、夫が健康保険から後期高齢者医療制度へ移ることによって、妻は健康保険の被扶養者から国保の被保険者になります。その場合、被扶養者であった人(65歳から74歳に限る)については、所得割はかかりません。また、均等割は半額となり、世帯割については被扶養者であった人のみで構成される世帯の場合のみ半額になります(最長2年)。
ただし、均等割、世帯割の軽減については、所得判定による7割軽減、5割軽減、に該当する場合、適用にはなりません。
備考 会社の健康保険(社会保険)とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などをさします。ただし、国民健康保険、国民健康保険組合(医師国民健康保険組合、建設国民健康保険組合など)は該当しません。
所得に応じた保険税の軽減措置
国民健康保険加入世帯で、前年中の総所得金額が一定基準以下の世帯は、国保税のうち「均等割」と「世帯割」の軽減を受けることができます。
ただし、軽減を判定する所得は、「事業専従者控除」や「譲渡所得の特別控除」の適用前の金額です。
また、その年の1月1日に65歳以上である人の公的年金所得からは15万円を差し引いて判定します。(公的年金所得が15万円に満たない場合はその全額を差し引きます。)
令和7年度
表:所得に応じた保険税の軽減措置(令和7年度)
| 項目 |
対象となる世帯 |
| 7割軽減 |
世帯で43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1) -1) 以下の所得
|
| 5割軽減 |
世帯で43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1) -1)+30万5千円×被保険者数(※2) 以下の所得 |
| 2割軽減 |
世帯で43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1) -1)+56万円×被保険者数(※2) 以下の所得
|
注釈1 給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満))又は125万円超(65歳以上)
注釈2 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)を含めず、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方(特定同一世帯所属者)を含む。
国民健康保険税の所得割の算定、軽減の判定などのために、世帯主及びその世帯に属する被保険者(加入者)の所得の申告が必要になります。
前年度の所得がない場合でも、申告がされていないと国民健康保険税の税額決定の上で、不利益が生じる場合があります。
早めの申告をお願いいたします。
未就学児の均等割軽減措置
子育て世帯の経済的な負担の軽減を図るため、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について、納税義務者の属する世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)である被保険者がいる場合は、未就学児に係る被保険者均等割額が2分の1軽減されることになりました。
未就学児均等割軽減額一覧表
| 軽減割合 |
医療分 |
後期高齢者支援分 |
| 均等割額 |
軽減額
(未就学児1人につき) |
均等割額 |
軽減額
(未就学児1人につき) |
| 7割軽減世帯 |
7,800円 |
3,900円 |
2,250円 |
1,125円 |
| 5割軽減世帯 |
13,000円 |
6,500円 |
3,750円 |
1,875円 |
| 2割軽減世帯 |
20,800円 |
10,400円 |
6,000円 |
3,000円 |
| 軽減なし世帯 |
26,000円 |
13,000円 |
7,500円 |
3,750円 |
年度の途中での加入・喪失した場合の保険税
年度途中で加入した場合の国保税は、加入した月から計算します。(届出の月ではありません。)
また、年度の途中で喪失した場合の国保税は、喪失した月の前月までの加入していた月数で計算します。
国民健康保険税の試算ができます
国民健康保険税を計算するためのエクセルシートです。加入する人の年齢区分と前年中の収入・所得を入力することで税額の計算ができます。
あくまで目安ですので、実際の税額とは異なる場合があります。
令和7年度の国民健康保険税(令和7年4月分から令和8年3月分)は、令和6年中の収入・所得で税額を計算します。
令和7年国保税計算シミュレーション(XLSM 39.9KB)
備考 Excelファイル編集機能がない端末では、ご利用いただけない場合があります。また、スマートフォンでは一部機能しない部分がありますのでご注意ください(スマートフォンで開く場合はMicrosoftExcelアプリ(無料)等をダウンロードする必要があります)。

 こども・子育て
こども・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者 休日当番医
休日当番医 ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクル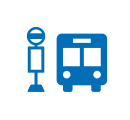 公共交通
公共交通 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引っ越し
住まい・引っ越し 就職・退職
就職・退職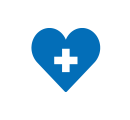 病気・けが
病気・けが おくやみ
おくやみ 施設案内・予約
施設案内・予約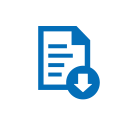 電子申請・申請書様式
電子申請・申請書様式 相談窓口
相談窓口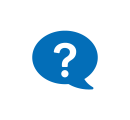 よくある質問
よくある質問 市長室へようこそ
市長室へようこそ 荒尾市議会
荒尾市議会 市政に参加する
市政に参加する 入札・契約
入札・契約





