体の機能を正常に維持するために欠かすことのできないビタミン。
実は水に溶ける「水溶性ビタミン」と油に溶ける「脂溶性ビタミン」があります。
現在13種類ありますが、多くのビタミンは、糖質・脂質・たんぱく質の代謝を滞りなく行う潤滑油のような働きをしています。
また、血管や粘膜、皮膚、骨などの健康を保ち、新陳代謝を促す働きにも関わっています。必要量はごくわずかですが、体内でほとんど作ることができない為、食べ物から摂取しないと、それぞれのビタミンに特有の欠乏症状を引き起こします。
水溶性ビタミン
- 水に溶けやすく、油脂には溶けにくい性質を持つ。
- ビタミンB群(B₁、B₂、B₆、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)とビタミンCの9種類。
- 血液などの体液に溶け込んでいて、余分なものは尿として排泄されるので、食べ物から毎食一定量をとる必要があります。
多く含む食品
ビタミンB群の一部…豚肉・レバー・青魚・大豆など
パントテン酸・葉酸・ビオチン・ビタミンC…ほうれん草・果物・えんどう豆・卵黄など
脂溶性ビタミン
- 水に溶けにくく、油脂に溶ける性質を持つ。
- ビタミンD、A、K、E(覚え方は「だけ」)の4種類。
- 水溶性と違って、肝臓に蓄積されるため、とり過ぎると頭痛や吐き気などの
過剰症を起こすものもあります。
※サプリメントなどでとる場合は注意が必要です。
多く含む食品
ビタミンD…【骨の形成に関わる】青背魚・きのこ類など
βカロテン(体内でビタミンAに変わる)【免疫力を高める】…緑黄色野菜
その他、うなぎ・キャベツ・ナッツ・しじみなど油といっしょにとると吸収がよくなります。
栄養の過不足がないように、
「毎食、バランスのとれた食事をする」ことを基本にしましょう。

 こども・子育て
こども・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者 休日当番医
休日当番医 ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクル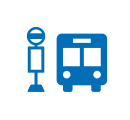 公共交通
公共交通 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引っ越し
住まい・引っ越し 就職・退職
就職・退職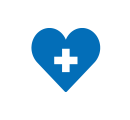 病気・けが
病気・けが おくやみ
おくやみ 施設案内・予約
施設案内・予約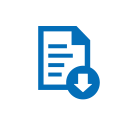 電子申請・申請書様式
電子申請・申請書様式 相談窓口
相談窓口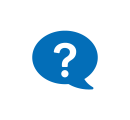 よくある質問
よくある質問 市長室へようこそ
市長室へようこそ 荒尾市議会
荒尾市議会 市政に参加する
市政に参加する 入札・契約
入札・契約




